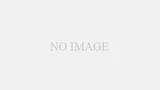接地抵抗計 電気を安全に使うのに欠かせないアース値を測定します。
電気工事で最初にするのが銅板埋込や継足しアース棒の打ち込みと、接地抵抗の測定作業です。
建設現場の初期段階で、先行して接地工事を施すのは一般的な流れで、かなり危険な場面もあり、周囲の状況に注意しながら作業を進めなくてはならないので、自ずと作業スピードは落ちるもので、
さらに測定値が規定値に達しない時は、焦りと共に作業工程が崩れて、余計に作業スピードが落ちるものです。
大掛かりなマンションや大規模な工場では、最低でもA種もしくはB種接地が求められるので、かなりシビアな値まで下げる必要があり、それなりの苦労をさせられることが多いものです。
戸建住宅のようにD種接地でいいのなら、何も考えなくても鼻歌交じりでも規定値に達するだろうけど、
D種接地以外では条件が悪いと、もう少しというところが下らず、かなり苦労することも少なくいのが正直なところで、多くの電気工事に携わるものが、同じような経験をしてることでしょう。
しかしいくら規定値に達しないからといって、そのまま放置したのでは最悪、受電出来なくなる可能性があるので、どんなことをしても規定値まで接地抵抗値を下げなくてはならないので、細かな調整にも接地抵抗計を活用して、こまめに値を計測する必要があるので、過酷な条件下でも正確に計測できる堅牢さを兼ね備えた接地抵抗計を用意する必要があります。
その意味からもこのページで主だった接地抵抗計を紹介しますので、ご覧ください。
日置電機 接地抵抗計
接地抵抗計も私が今使ってるものから紹介します。
これは個人的な感想ですが、
私は日置電機のテスター・絶縁抵抗計を使ってて、その流というわけじゃないけど接地抵抗計も今は日置電機の国際規格取得の防塵・防水接地抵抗計を使ってます。
接地抵抗を測定する環境はお世辞にも良いとは言い難いことが多く、汚れたり下手すりゃ水溜まりに落してしまうことも考えられるような状況なので、防塵・防水設計の接地抵抗計はとっても使い勝手がいいので、見付てすぐに買ってしまいました。
実際、使ってみた感想もとっても使いやすくて気に入ってるし、
仮に壊れたとしてもまた同じものをリピします。
これ以上に良い物が無かったらの話だけどね。
日置電機(HIOKI) 防塵・防水接地抵抗計
改めてAIでIP65とIP67に付いて調べてみました。
IP65とIP67は、IPコード(Ingress Protection Code:イングレスプロテクションコード)と呼ばれる国際規格で、電気製品の防塵性能と防水性能を示すものです。
このIPコードは、IEC(国際電気標準会議)によって定められ、日本でもJIS(日本工業規格)で採用されています。
これを見ても現場で使うときの汚れや一時的な水没程度なら、何ら問題にならない性能を有してることが分かるので、現場でも安心して使ってるけど、もちろん大切に扱ってることは言うまでもないけどね。
実際に使っても良い物だと言えるので、自信を持ってお薦めします。
アナログ接地抵抗計
日置電機の接地抵抗計の詳しい仕様は日置電機(HIOKI)のサイトで確認してください。
共立電気計器(KYORITSU) 接地抵抗計
この二つなら、ほとんどの現場に対応できるでしょう。
どちらも防塵・防滴設計なので少々汚れても洗えばきれいにできるので、あまり気にすることなく測定に集中できます。
この点はやっぱり有難いよな。
デジタル簡易接地抵抗計
2極法簡易測定専用器で接地棒の設置が必要ないので、既存の建物内での簡易接地測定に便利な機種です。
通常の3極法の測定が出来れば、ほとんどの機種で2極法簡易測定が可能なので、あえて必要かと問われれば、
ちょっと?マークが付くかもしれないけど、わざわざ接地抵抗計を持ち出して2極法簡易測定の準備をしなくても、現場に着いたらすぐに測定できるので、便利は便利だよな。
共立電気計器の接地抵抗計の詳しい仕様は共立電気計器(KYORITSU)のサイトで確認してください。
三和電気計器(sanwa)アナログ接地抵抗計
三和電気計器(sanwa)にはデジタル接地抵抗計が見当たらない。
三和電気計器の接地抵抗計の詳しい仕様は三和電気計器(sanwa)のサイトで確認してください。